こんにちは。アメリカ東海岸在住のankomomです。こどもたちの学校の新学年が始まり、部活のトライアウトも終わり、今日は長女の中学校の部活説明会parent meetingに行ってきました。運動部の説明会は毎シーズン毎(秋シーズン、冬シーズン、春シーズン)にシーズンの始まる頃にあって、全体の説明会の後、スポーツごとに分かれて説明があります。全体説明会の内容はだいたい「部活に参加するための条件」「学校のスポーツで守ってほしいルール」「ブースタークラブについて」についてです。去年までと違って、部活に参加するための条件に「前の学期 に “F” の成績を2つ取ったら参加できない」「前の学期に “F” もしくは “D” を1つをとって、かつ何か問題行動が1回あったら参加できない」の成績要件はなくなって、主には学校の出席日数と、スポーツ精神に反する行動をとらない、の条件だけになったようでした。
ブースタークラブは、運動部の部活動に必要なお金を集めたり、設備の寄付をしたりする親のボランティア活動で、ブースタークラブの主催する大きなイベントは毎シーズン終わりのathletic banquetと、ハロウィーンダンスです。athletic banquetではathletic directorの挨拶の後、スポーツごとに分かれてAwardの発表とシーズンの締めくくりの会をします。秋と冬は屋内ですが、春スポーツのathletic banquetは運動場に3,4台のフードトラックとDJも来てくれてとても賑やかです。ハロウィーンダンスは、息子の野球の友達のお母さんからは「ダンスしないでただその辺でしゃべってるだけの子もたくさんいる」とも聞き、息子にもぜひ行ってみるように勧めていたのですが、結局一度も行かなかったので、どんなものだかわかりません。長女が行ってみてくれることに期待です。
ブースタークラブ本部以外の保護者のボランティアには、ホームゲームでのコンセッション販売(観客向けに飲み物やスナックを試合中に販売しています)+ホームゲームでの観客の入場料チケット係(この地区の中学校ではどのスポーツも1人5ドル、高校生以下とシニアは無料、でした)が毎回あって、ボランティアできる日を自主的にオンラインページから登録する仕組みになっています。その他はスポーツ毎に試合の日の選手用のスナックやドリンク、スポーツによって試合の日の手伝い(例えばクロスカントリーでは、ゴールラインで順位札を渡す、など)があったり、場合によっては保護者がアシスタントコーチをしてくれていたりします。野球では「バックミュージック係」もあって、立候補してくれた保護者が、毎回大きなスピーカーを持ってきては、選手毎のウォークアップソングを打席に立つ度に流してくれたり、イニングの変わる時にも音楽を流してくれたりしていました。試合の日のスナックもスポーツによって違っていて、例えばサッカーはコーチがまとめて買っておいてくれて保護者はコーチのアカウントに任意でdonationする、クロスカントリーはその日ごとに保護者の誰かが学校まで届ける、という具合でした。野球は試合時間が長いからか、そういう伝統なのか、毎回だいぶ食事らしい補食を届けることになっていて、息子が中1の時は当時3年生のD君のレストランをしているご両親がなんと「うちが毎回メインは持ってくるから、他の人で飲み物とその他のスナックを持ってきてね」と申し出てくれ、選手たちは有難く美味しそうなサンドイッチやチキンを毎回いただいていました。息子が中2の時は補食もできる日立候補制でしたが、中3の時は、またD君のご両親が弟が中学生になったから(野球はしていないものの)有料でよかったら届けるよ、と提案してくれて、お願いしていました。息子の中学野球部の時の補食係は考えてみるとだいぶ大変で(私は普段バス通勤をしていますが、補食を届けるとなると、仕事を抜けてバスで家まで帰り、車でどこかに人数分の美味しそうなものを買いに行って15時から15時20分の間にグラウンドに届けないといけない、特にアウェイの試合の日は遅れたら選手の乗ったバスが出発してしまうことにもなり、厳密に時間を逆算して計算しようと考えてみてもぴったりに行ける気がせず・・)、もっぱら私は入場料チケット係とコンセッション販売をやっていました。長女の今シーズンのクロスカントリーのスナックは、朝から試合開始前までの間いつ届けてもいいようなので、今回はスナック飲み物のお届けにも立候補してみようかと思います。
読んでいただいて、ありがとうございました!
【余談:最近読んでよかった本・面白かった本】
「樹木たちの知られざる生活 森林管理官が聴いた森の声」ペーター・ヴォールレーベン著、長谷川圭訳、早川書房
樹木同士のコミュニケーションや社会生活、昆虫や動物との関わり。草食動物に葉を食べられたら、葉に有害物質を集めつつガスを発散して周りの樹にも危険を知らせる・・虫が葉を食べ始めたらその虫の天敵が好きなにおいを発散して、その虫の天敵を呼ぶ・・数年ごとに花を咲かせるのは、実を食料にする草食動物が減った頃にいっせいに実をつける生き残り戦略・・など。周りに光があふれているときにすぐに外に向かって枝を伸ばすかどうか、水分を節約して使うか贅沢に使うか・・・性格とでもいえるような木々の個性についても語られています。まさに題名通り「樹木たちの知られざる生活」が綴られていて、読んでいてとても面白かったです。日常生活で家の周りにある木も、何かを感じて何かをささやきながら過ごしている、という気がしてきて、日常の風景がちょっと違ってみえてくる本でした。
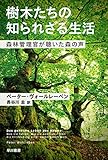
樹木たちの知られざる生活 森林管理官が聴いた森の声 (ハヤカワ文庫NF)
アメリカ東海岸在住。こども3人の子育てをしつつ、夫婦ともに研究留学中です。息子の野球、こどもたちの学校、アメリカでのお出かけスポットなど、アメリカ生活の日々のあれこれをぼちぼちと綴っていきたいと思います。
何かの参考に・・楽しんでいただけたら嬉しいです。
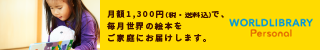

コメントを残す